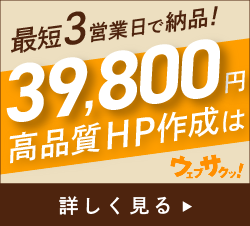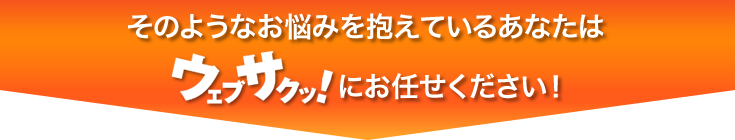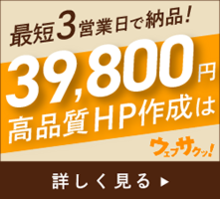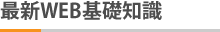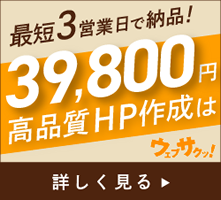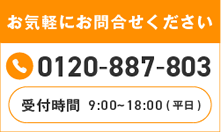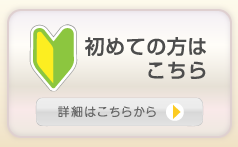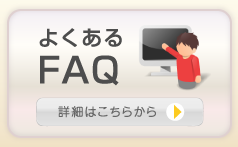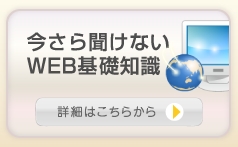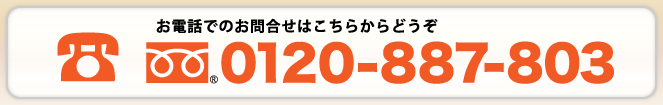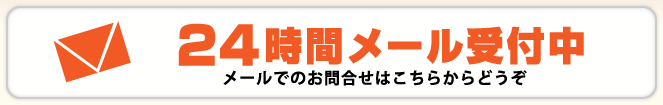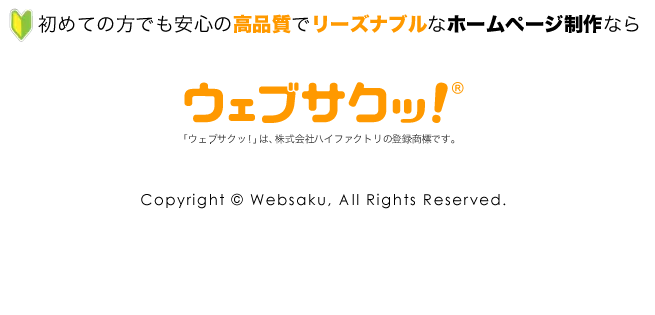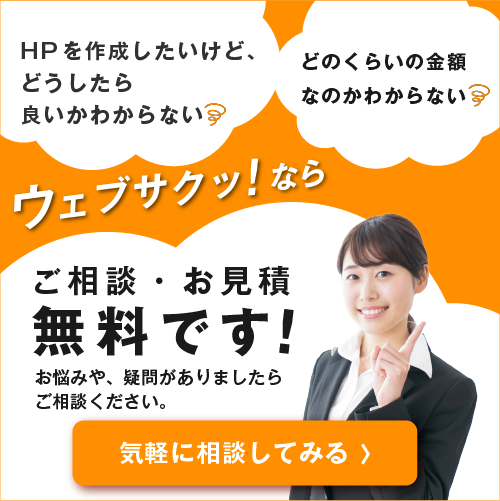
FAQ(よくある質問)の作り方を5ステップで解説!注意すべきポイントとは

FAQ(よくある質問)を作りたくても、具体的な作り方がわからず困っている方は多いのではないでしょうか。
FAQ(よくある質問)の作り方はシンプルですが、価値あるページに仕上げるためにはメリットやポイントの理解が重要です。
この記事では、FAQ(よくある質問)の作り方やメリットをご紹介します。
目次
FAQ(よくある質問)に作り方はある?

FAQの作り方は、質問と回答のセットを列挙することです。
FAQ作成の際は、閲覧者にメリットを与えることがポイント。
そのために、まずは「FAQ(よくある質問)とは何か」を理解しましょう。
FAQ作成の際は、閲覧者にメリットを与えることがポイント。
そのために、まずは「FAQ(よくある質問)とは何か」を理解しましょう。
FAQ(よくある質問)とは

FAQとは「Frequently Asked Questions」の略語であり、日本語では「よくある質問」と表記します。
頻繁に質問される内容をあらかじめ回答とセットでページにまとめることで、「顧客が問い合わせる手間」と「社員が問い合わせに対応する手間」を削減することが目的です。
また、FAQと「Q&A」を混同してしまうケースがよくみられます。
主な違いは、「Q&A」ではさまざまな質問と回答を紹介する点です。
FAQでは頻繁に問い合わせを受ける内容のみをまとめているのに対し、「Q&A」では問い合わせの頻度を重視せずに多くの質問を紹介します。
ただ、明確には線引きされず混同されているのが実情です。
頻繁に質問される内容をあらかじめ回答とセットでページにまとめることで、「顧客が問い合わせる手間」と「社員が問い合わせに対応する手間」を削減することが目的です。
また、FAQと「Q&A」を混同してしまうケースがよくみられます。
主な違いは、「Q&A」ではさまざまな質問と回答を紹介する点です。
FAQでは頻繁に問い合わせを受ける内容のみをまとめているのに対し、「Q&A」では問い合わせの頻度を重視せずに多くの質問を紹介します。
ただ、明確には線引きされず混同されているのが実情です。
FAQ(よくある質問)の種類

FAQ(よくある質問)の種類は対象の閲覧者により以下の3つに分類されます。
- 顧客向け
- 社員向け
- コールセンター職員向け
1.顧客向け
顧客向けのFAQは、サービスや商品に関する疑問を解決することを目的にECサイトなどに設置されます。
顧客が自主的に疑問を解消するための利用を想定しているため、わかりやすさが重要です。
顧客が自主的に疑問を解消するための利用を想定しているため、わかりやすさが重要です。
2.社員向け
社員向けのFAQは、事務作業やシステムの利用方法などに関する疑問を解決するために設けられます。
わざわざ担当部門に問い合わせる必要性が薄まるので、質問する側と質問される側の双方の手間が省けます。
わざわざ担当部門に問い合わせる必要性が薄まるので、質問する側と質問される側の双方の手間が省けます。
3.コールセンター職員向け
コールセンター職員向けのFAQは、質問と回答をセットとした形式のマニュアルです。
コールセンター部門に蓄積された情報をFAQとして共有することで、属人化の防止や経験の浅い職員の手助けとなります。
なお、この記事では顧客向けのFAQについて解説します。
コールセンター部門に蓄積された情報をFAQとして共有することで、属人化の防止や経験の浅い職員の手助けとなります。
なお、この記事では顧客向けのFAQについて解説します。
FAQ(よくある質問)を作成するメリット

価値のあるFAQを作成するには、FAQのメリットを理解することが大切です。
- 顧客満足度のアップ
- 問い合わせ業務の負担軽減
- 属人化の防止
1.顧客満足度のアップ
1つ目は「顧客満足度のアップ」です。
商品やサービスについて疑問を持ったとしても、わざわざ問い合わせるのを億劫に感じた経験はないでしょうか。
FAQを設けておけば、顧客はページを閲覧するだけで疑問を解決できます。
また、問い合わせる意思があったとしても、営業時間外だったりコールセンターが混雑していたりするケースもあるでしょう。
翌営業日まで疑問を抱えたままにさせたり、コールセンターにつながるまで待たせたりすると、顧客満足度が低下しかねません。
FAQならば24時間いつでも自分で疑問を解決できるため、顧客満足の低下を防止できます。
商品やサービスについて疑問を持ったとしても、わざわざ問い合わせるのを億劫に感じた経験はないでしょうか。
FAQを設けておけば、顧客はページを閲覧するだけで疑問を解決できます。
また、問い合わせる意思があったとしても、営業時間外だったりコールセンターが混雑していたりするケースもあるでしょう。
翌営業日まで疑問を抱えたままにさせたり、コールセンターにつながるまで待たせたりすると、顧客満足度が低下しかねません。
FAQならば24時間いつでも自分で疑問を解決できるため、顧客満足の低下を防止できます。
2.問い合わせ業務の負担軽減
2つ目は「問い合わせ業務の負担軽減」です。
FAQを設ければ、顧客からの問い合わせは限定されます。
問い合わせ件数が減少すれば、リソースを分析や調査に費やせるでしょう。
そのリソースでFAQを更新すれば、いっそう問い合わせ件数を減らせることにつながり、顧客満足度のアップと問い合わせ業務の負担軽減効果が高まります。
FAQを設ければ、顧客からの問い合わせは限定されます。
問い合わせ件数が減少すれば、リソースを分析や調査に費やせるでしょう。
そのリソースでFAQを更新すれば、いっそう問い合わせ件数を減らせることにつながり、顧客満足度のアップと問い合わせ業務の負担軽減効果が高まります。
3.属人化の防止
3つ目は「属人化の防止」です。
問い合わせ内容によっては、「社員Aなら回答できるが社員Bは回答できない」などのケースが発生します。
その際は社員Aの知識を他社員に共有すべきですが、なかなか時間を取れないことも多いでしょう。
そこでそれぞれの社員が持つ知識をFAQにまとめておけば、社員同士で知識を共有できます。
問い合わせ内容によっては、「社員Aなら回答できるが社員Bは回答できない」などのケースが発生します。
その際は社員Aの知識を他社員に共有すべきですが、なかなか時間を取れないことも多いでしょう。
そこでそれぞれの社員が持つ知識をFAQにまとめておけば、社員同士で知識を共有できます。
FAQ(よくある質問)の作り方を5ステップで解説

FAQの作り方を具体的に5ステップで解説します。
2ステップまでで基盤は完成するので、3ステップ以降での目的はより充実したページに仕上げることです。
2ステップまでで基盤は完成するので、3ステップ以降での目的はより充実したページに仕上げることです。
- FAQ(よくある質問)を集める
- FAQ(よくある質問)を分類する
- 客観的な意見で充実度を確認する
- ロールプレイングで確認する
- FAQ(よくある質問)を追加・変更する
1.FAQ(よくある質問)を集める
1ステップ目は「FAQ(よくある質問)を集めること」です。
まずはFAQで紹介する素材を集めましょう。
実際に顧客から頻繁に問い合わせを受けた質問を集めれば、顧客が知りたい情報が揃います。
問い合わせ担当部門やオペレーターからヒアリングを行えば効率的に素材を集められます。
また、同業他社が公開しているFAQを参考にするのも有効な手段です。
まずはFAQで紹介する素材を集めましょう。
実際に顧客から頻繁に問い合わせを受けた質問を集めれば、顧客が知りたい情報が揃います。
問い合わせ担当部門やオペレーターからヒアリングを行えば効率的に素材を集められます。
また、同業他社が公開しているFAQを参考にするのも有効な手段です。
2.FAQ(よくある質問)を分類する
2ステップ目は「FAQ(よくある質問)を分類すること」です。
素材を集めたら、それぞれを分類します。
FAQ作成の目的は閲覧者の疑問解消であり、分類を行わなければ、そもそも知りたい情報を見つけられない可能性が想定されます。
分類の基準は、顧客視点で設定しましょう。
素材を集めたら、それぞれを分類します。
FAQ作成の目的は閲覧者の疑問解消であり、分類を行わなければ、そもそも知りたい情報を見つけられない可能性が想定されます。
分類の基準は、顧客視点で設定しましょう。
3.客観的な意見で充実度を確認する
3ステップ目は「客観的な意見で充実度を確認すること」です。
社員だけでFAQを作成すると、顧客視点の考えを見落としてしまう可能性が高いので、第三者の客観的な意見が重要です。
家族や友人など、事業に精通していない人からの意見を反映させましょう。
社員だけでFAQを作成すると、顧客視点の考えを見落としてしまう可能性が高いので、第三者の客観的な意見が重要です。
家族や友人など、事業に精通していない人からの意見を反映させましょう。
4.ロールプレイングで確認する
4ステップ目は「ロールプレイングで確認すること」です。
顧客の視点に立ち、FAQで悩みが解決するかをロールプレイングで確認しましょう。
いざ顧客の視点に立つと、FAQでどのページを閲覧すればいいかわからなかったり、気になる疑問が紹介されていないことに気が付いたりする可能性があります。
FAQ(よくある質問)を閲覧する人の視点から確認しましょう。
顧客の視点に立ち、FAQで悩みが解決するかをロールプレイングで確認しましょう。
いざ顧客の視点に立つと、FAQでどのページを閲覧すればいいかわからなかったり、気になる疑問が紹介されていないことに気が付いたりする可能性があります。
FAQ(よくある質問)を閲覧する人の視点から確認しましょう。
5.FAQ(よくある質問)を追加・変更する
5ステップ目は「FAQ(よくある質問)を追加・変更すること」です。
商品やサービス、業界が変化すれば、顧客が抱える疑問は変化します。
定期的にFAQを追加・変更し、顧客が満足できるページに仕上げましょう。
商品やサービス、業界が変化すれば、顧客が抱える疑問は変化します。
定期的にFAQを追加・変更し、顧客が満足できるページに仕上げましょう。
FAQ(よくある質問)の作り方におけるポイント

FAQの作り方におけるポイントを5つご紹介します。
これらのポイントを押さえれば、FAQを作成する価値が高まります。
これらのポイントを押さえれば、FAQを作成する価値が高まります。
- 顧客視点でわかりやすさを重視する
- キーワード検索機能を設定する
- カテゴライズして表示する
- 写真・動画を活用する
- 関連するページへ誘導する
1.顧客視点でわかりやすさを重視する
1つ目は「顧客視点でわかりやすさを重視すること」です。
たとえば、回答の項目では結論ファーストを意識しましょう。
まず結論を述べてから詳細を補足することで、顧客の疑問をスピーディーに解決できます。
たとえば、回答の項目では結論ファーストを意識しましょう。
まず結論を述べてから詳細を補足することで、顧客の疑問をスピーディーに解決できます。
2.キーワード検索機能を設定する
2つ目は「キーワード検索機能を設定すること」です。
FAQの数が多いと、必要な情報を見つけるだけでも苦労します。
キーワード検索機能を設定すれば、求めている情報に関連する項目をすぐに見つけられます。
FAQの数が多いと、必要な情報を見つけるだけでも苦労します。
キーワード検索機能を設定すれば、求めている情報に関連する項目をすぐに見つけられます。
3.カテゴライズして表示する
3つ目は「カテゴライズして表示すること」です。
カテゴライズするメリットは、顧客が求めている情報に辿り着きやすいことです。
また、明確な疑問ではなく「〇〇について詳しく知りたい」などのニーズに対しても、カテゴライズが顧客満足度のアップに役立ちます。
カテゴライズするメリットは、顧客が求めている情報に辿り着きやすいことです。
また、明確な疑問ではなく「〇〇について詳しく知りたい」などのニーズに対しても、カテゴライズが顧客満足度のアップに役立ちます。
4.写真・動画を活用する
4つ目は「写真・動画を活用すること」です。
内容によっては、テキストだけではなく写真や動画を活用した方がわかりやすい場合があるでしょう。
疑問の解決がFAQ作成の目的であるので、わかりやすさを高める工夫が重要です。
内容によっては、テキストだけではなく写真や動画を活用した方がわかりやすい場合があるでしょう。
疑問の解決がFAQ作成の目的であるので、わかりやすさを高める工夫が重要です。
5.関連するページへ誘導する
5つ目は「関連するページへ誘導すること」です。
顧客が気になりそうな内容を予想し、関連するページへ誘導しましょう。
閲覧者が少ない手間で多くの有益な情報を得られる仕組みが顧客満足度アップにつながります。
顧客が気になりそうな内容を予想し、関連するページへ誘導しましょう。
閲覧者が少ない手間で多くの有益な情報を得られる仕組みが顧客満足度アップにつながります。
まとめ:FAQ(よくある質問)の作り方を理解し顧客満足度アップ!

今回はFAQ(よくある質問)の作り方について解説しました。
工夫を凝らしたFAQを作成すれば、いっそう顧客満足のアップや問い合わせ業務の負担軽減を図れます。
ぜひ本記事を参考に、FAQを作成してみてください。
工夫を凝らしたFAQを作成すれば、いっそう顧客満足のアップや問い合わせ業務の負担軽減を図れます。
ぜひ本記事を参考に、FAQを作成してみてください。
|
2025/03/31 4月1日(火)営業時間変更のお知らせ |
|
2024/12/18 年末年始休暇のお知らせ |
|
2024/11/13 【復旧のご報告とお詫び】メール障害について |
|
2024/09/19 【重要なお知らせ】月額費用価格改定について |
|
2024/08/15 8/16(金)台風7号接近に伴うテレワーク実施のお知らせ |